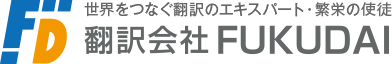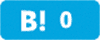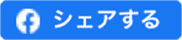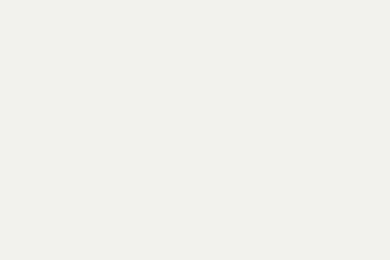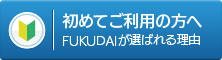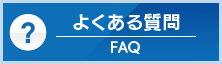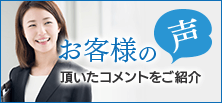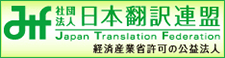翻訳コラム
2018.12.27
英語と日本語の違いとは?翻訳表現から見る

「英語を長年勉強しているのになかなか上達しない」、「英文を作ろうとするとどうしても上手くいかない」など、英語学習に関する悩みというのは人によってさまざまです。
では、こうした英語学習の問題はどう解決すればいいのでしょうか。
大切なことは、英語と日本語は全く異なる言語であるという点をきちんと理解しなければならないということです。きちんと理解することで、自分が苦手としている部分が明確になる、効率的な学習方法が見つかるものです。今回は、言語的な意味で、英語と日本語の違いを、詳しく解説していきます。
Index
英語と日本語の言語が大きく違う理由
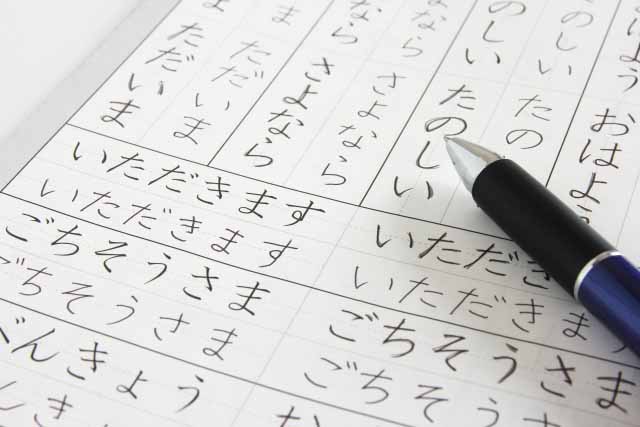
英語と日本語に限らず、どんな言葉であっても母国語以外の言葉を完璧に理解するというのは、簡単なことではありません。なぜなら、言語はその国の文化の影響を大きく受けるものだからです。
例えば、日本には「出る杭は打たれる」という言葉があるように、日本人は過度な自己主張はせず、周囲との協調を大切にする傾向があります。すべてのことを言葉に出さなくても、互いに相手の気持ちや意図を察したり、本音と建て前が存在したりというのも日本ならではの文化です。
【参考記事】⇒ 英語と日本語の構造的な違いが英和翻訳の難しい理由です。
一方、英語圏の人たちはというと、感情を豊かに表現し、自分の気持ちをはっきりと言葉にして表す傾向
が強いといえます。自分らしくいることに誇りを持ち、「貴方は貴方、私は私」と明確に線引きをする特徴があるのです。こうした価値観および文化の違いは、言語にも大きく影響をします。どんなに一生懸命英語を勉強しても、この違いを理解していなければ使える英語を身につけることは難しいといえるでしょう。
英語と日本語の文法構造の違い
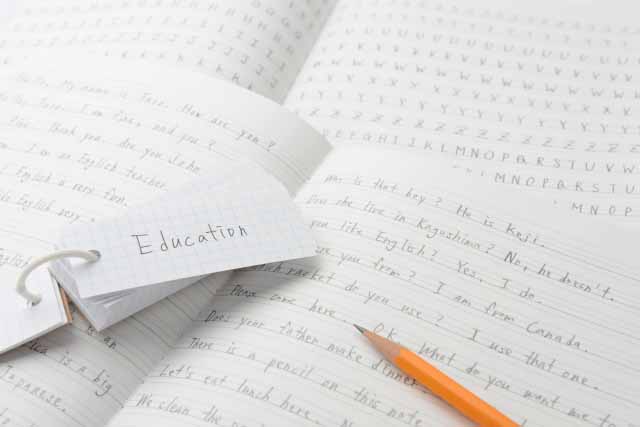
日本人が英語を勉強して最初に戸惑うのが、文法の違いについてです。日本語というのはSOV(主語+目的語+動詞)という語順によって文章が構成されるのが基本ですが、英語の場合はSVO(主語+動詞+目的語)という語順によって文章が作られます。
【参考記事】⇒ 英語の構文(文法)を理解することは英文和訳が上達するポイントです。
語順(SVO vs SOV)
日本語は SOV(主語‐目的語‐動詞) が基本語順ですが、英語は SVO(主語‐動詞‐目的語) が基本です。
例:
- 日本語:「私は英語を勉強する」
- 英語:I study English.
この語順の違いにより、英文では動詞近くに副詞や修飾語が来ることが多く、文頭・文末の語順の自由度が日本語よりも狭くなります。
また、英語は修飾語を動詞の前後に配置できず、位置を誤ると意味が変わることがあります。
冠詞・複数形・時制の扱い
英語には 冠詞 (a / the / zero article) や 複数形 (–s / –es)、時制 (過去/現在/未来などの活用) があり、これらは日本語にはありません。
- 冠詞: ‘a car’ と ‘the car’ でニュアンスが異なる(不特定/特定)
- 複数形: ‘apple / apples’ のように単数/複数による区別
時制・完了形:英語は時制に敏感で、完了形・進行形といった複雑な構文が存在する
これらの扱いは日本語には対応概念がないため、特に和訳・英訳時に誤用・省略・過剰翻訳が起きやすいポイントです。
英語と日本語の文章表現の違い

英語と日本語は文法だけではなく、文章表現も異なる部分が多数あります。では、その違いについて詳しく紹介します。
【参考記事】⇒ 和英翻訳でよくつまずく、英語にしにくい日本語表現
否定疑問文・質問文のニュアンスの差
日本語で「〜ではないですか?」と尋ねる「否定疑問文」は英語化するときに混乱を招きがちです。英語の否定疑問文で答える “Yes / No” は、日本語とは逆の意味を含むケースがあります。
例:
- “Don’t you like English?” → “Yes, I do.” (はい、好きです)
- “Don’t you eat meat?” → “No, I don’t.” (いいえ、食べません)
ここで注意したいのは、「Yes / No」応答の扱い。多くの日本人は「いいえ/はい」で混乱しやすいため、英語流の回答パターンに慣れておく必要があります。
さらに、英語の疑問文には 否定疑問文 だけでなく、付加疑問文 (tag question) や 間接疑問文 もあり、それぞれ表現スタイルが異なります。例えば “You like English, don’t you?” といった付加疑問文では、日本語での直訳はぎこちなくなりがちです。
主語の有無
日本語では主語が省略されていても意味が通じやすく、文脈で補えることが多いです。
例:
- 「(私は)昨日映画を見た」
- 「(彼は)学生です」
一方、英語では主語を省略できません。必ず “I / he / she / they / we / it” などを入れる必要があります。
例:
- 正:I watched a movie yesterday.
- 誤:Watched a movie yesterday.
このような主語の省略可否の違いは、翻訳時にしばしば見落とされ、英訳で不完全な文ができてしまう原因になります。
修飾語の語順・位置の差異
日本語では修飾語(形容詞・副詞・修飾節など)が修飾対象の前に置かれることが一般的ですが、英語は修飾語の順序・位置が厳格です(前置修飾・後置修飾、限定句・非限定句など)。
例:
- 日本語:赤い大きな車 → 英語:a large red car
- 日本語:昨日買った本 → 英語:the book (that) I bought yesterday
また、日本語では「〜のために」「〜によって」などの句を後ろに置くことが多いが、英語では前置詞句(for, by, because of など)や関係代名詞句を使って前置的に配置したり、文末に配置したり、文意を調整する柔軟性があります。
英語と日本語の語彙・語形成の違い
英語と日本語では文法構造だけでなく、語彙の成り立ちや単語の使われ方にも大きな差があります。翻訳や日常のコミュニケーションにおいて、この違いを理解していないと誤解を生む原因となります。以下では、両言語の語彙における特徴を具体的に見ていきましょう。
日本語と英語の文字体系の差異
日本語というのは、文字一つひとつに意味を持つ「表意文字」の漢字と、一つひとつに音素がある「表音文字」(ひらがな・カタカナ)を組み合わせて使う言語です。これに対して、英語は表音文字であるアルファベットのみを用いて表現します。
そのため日本語では、多少言葉を言い間違えたり、漢字を読み間違えても、文脈や文字の形から意味を推測できることが多いのに対し、英語では発音や綴りの誤りが直接意味の理解を妨げやすいという特徴があります。
単語の構成と表現の違い
また、英語と日本語では語彙の作り方にも違いがあります。例えば、日本語では「湯」という一語で「お湯」を表現できますが、英語では「hot water」と二語を組み合わせて初めて同じ意味を表せます。つまり、日本語では単一の語にまとまった意味が込められる傾向が強い一方、英語は複数の語を組み合わせて概念を明示的に説明する傾向があります。
さらに、日本語は漢字の組み合わせによって新しい語を生み出す「造語力」に優れており、例えば「情報」「環境」「関係」などの熟語は、複数の漢字を組み合わせるだけで抽象的な概念を表すことができます。対して英語では、接頭辞・接尾辞の付加や語の組み合わせによって新しい単語を形成します。たとえば「inform(知らせる)」から「information(情報)」「informative(有益な)」と派生させるといった具合です。
意味範囲とニュアンスのギャップ
さらに注意すべきなのは、単語が持つ意味範囲の違いです。日本語の「報告」は英語で単に “report” と訳す場合もありますが、状況によっては “inform”“notify”“account” などが適切な場合もあります。このように、一語に対応する訳語が複数存在するため、翻訳では文脈に応じた使い分けが不可欠です。
また、英語の単語には多義性(polysemy)が多く見られます。例えば “charge” は「請求する」「非難する」「突撃する」「充電する」など、複数の意味を持つため、日本語の一対一の語と単純に対応させるのは困難です。この点が、翻訳者がニュアンスを見極める上での大きな課題となります。
語彙の豊かさ・借用語・和製英語
日本語は外来語を柔軟に取り入れる言語であり、カタカナ語として日常的に使われる語彙が非常に多いです。その中には、和製英語(英語圏では使われない・意味が異なる英語風語) も多数含まれます。翻訳実務では、これらをそのまま英語に置き換えると誤訳になる危険があります。
誤訳例:
- 「クレーム」 → claim(誤り)。正しくは complaint。
- 「ヒアリング」 → hearing(誤り)。正しくは interview や listening session など。
- 「オーダーメード」 → order-made(誤り)。正しくは custom-made / made-to-order。
英語圏にはそもそもその語彙概念が存在しない場合や、似た語でもニュアンスが異なることが頻繁にあります。
また、英語自身は他言語からの借用語を多数含んでおり、語彙の多様性と重層性が非常に高いです。同義語・類語の選択肢が多く、文脈や語感で最適語を選ぶ判断力が求められます。
翻訳実務で気をつけるべきポイント(誤訳例付き)
以下は、翻訳者が語彙・語形成差異を意識して使う際に特に注意すべきポイントと、典型的な誤訳例およびその修正案です。
| 項目 | 落とし穴/誤訳例 | 修正・注意点 |
|---|---|---|
| 和製英語の誤用 | 「コンセント」 → concent(誤り) | 正しくは electrical outlet / socket など。 |
| 多義語の読み替えミス | “charge” を「請求する」と訳したが文脈は「責める」の意味 | 文脈を見て “accuse / blame / charge / fee” を使い分ける。 |
| 語派生の誤用 | “informative” を「情報的な」ではなく「有益な」に訳すべき場面で「情報的な」と直訳 | 派生語の意味変化を意識して「有益な・参考になる」など意訳を使う。 |
| 単語粒度の違い | 日本語「湯」 → hot water(二語) | 英語では細かく分けて表現する必要がある。 |
| カタカナ語そのまま英訳 | 「アイスコーヒー」 → ice coffee(誤り) | 正しくは iced coffee。 |
翻訳時のチェック項目
翻訳を行う際に以下の項目を意識することで、より自然で正確な英語表現へと近づけることができます。
| チェック項目 | 内容 |
|---|---|
| 主語の明示 | 英語文には必ず主語を入れる |
| 語順の厳守 | SVO の語順を崩さない |
| 冠詞・複数形処理 | 必要なら a / the / s を付ける/省略しない |
| 意味範囲の確認 | 日本語語・英語語のニュアンスの違いを確認 |
| 修飾語の位置調整 | 日本語からそのまま訳さず、英語の修飾順に直す |
| 疑問文応答処理 | 否定疑問文など回答パターンを正しく扱う |
英語翻訳でお困りの際はぜひ翻訳会社FUKUDAIへご相談ください

ここまで、英語と日本語の 構造的・表現的・語彙的 な違いを、具体例を交えて見てきました。特に、「表現の違い」に注目することで、翻訳で躓きがちなポイントを明確にできます。
もし、英語翻訳(英和翻訳や和英翻訳)が難しいと感じた場合には、ぜひ翻訳会社FUKUDAIまでお気軽にご相談ください。
関連記事
和文英訳のコツと翻訳会社依頼の注意点を解説
英文和訳が上達する方法は?翻訳会社に依頼するメリットも解説
和英翻訳でよくつまずく、英語にしにくい日本語表現
英和翻訳で自然な訳文に仕上げるための7つのポイント
監修者
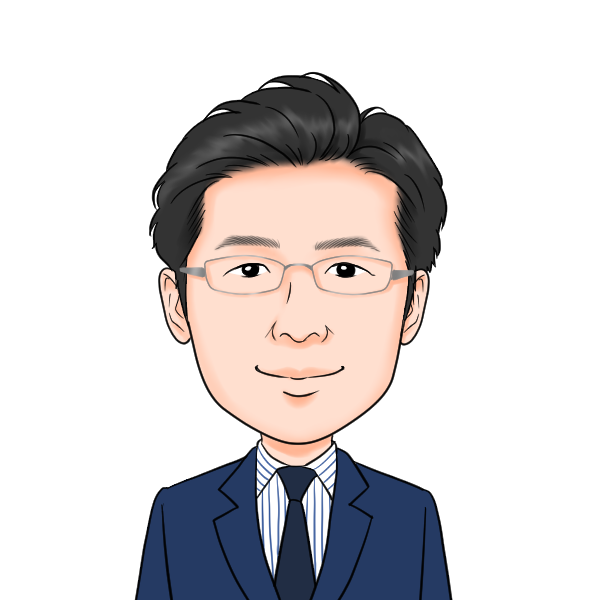
翻訳会社FUKUDAI 代表取締役
鈴木 宏基